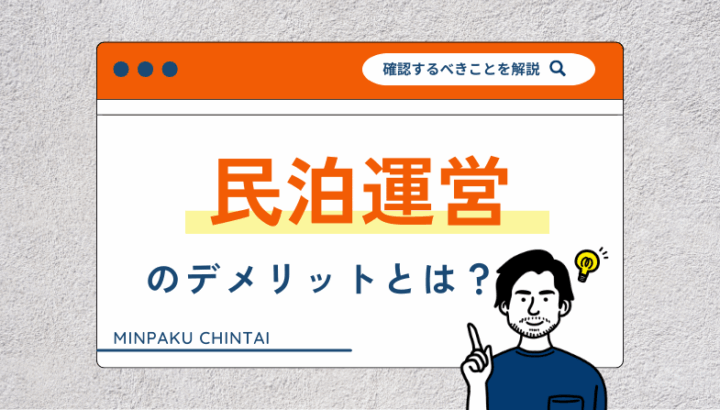民泊の許可申請のやり方を解説!事前の確認事項と必要書類は?
「民泊を始めたいけど、許可申請や届出のやり方がわからない」と感じている方はいませんか?
今回の記事では、民泊を始める際の届出のやり方を解説します。具体的な手順や用意する書類、確認事項なども紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
CONTENTS
民泊の許可申請はどうやってやる?
民泊を始める際には、必ず各自治体の条例と法律に乗っ取った正しい方法で民泊の運営許可を取得する事が重要です。
まずは、具体的な申請方法を解説していきます。
1.営業形態を決める
安心安全に利用できる民泊施設を運営するために、民泊の営業形態を決定しておきましょう。
民泊新法
民泊新法は、2018年6月15日に施行された法律で、民泊事業を行うための基本的なルールを定めています。この法律の目的は、民泊の健全な発展と利用者の安全を確保することで、宿泊施設の衛生管理や防火対策、近隣住民への配慮などが求められます。
民泊新法の大きな特徴は、年間180日以内の営業日数制限があることです。また、自治体に届け出を行えば事業が開始できるので、ハードルが低く始めやすいのも特徴です。
旅館業(簡易宿所)
旅館業法(簡易宿所)は、宿泊施設の衛生管理や安全対策を確保し、利用者の健康と安全を守ることを目的とした法律です。
通常、民泊は簡易宿所での申請をするのが一般的です。施設の構造や設備が一定の基準を満たしたうえで、自治体に営業許可を取得する必要があります。申請へのハードルが最も高いですが、許可が下りれば営業日数が無制限になるというメリットもあります。
特区民泊
特区民泊は、国家戦略特区に指定された地域でのみ認められる民泊形態で、地域の特性を活かして経済成長を促進するために、規制緩和や特別な措置が講じられる地域のことを言います。
特区民泊の特徴は、最低宿泊日数が2泊3日であることです。1泊のみの宿泊は受け付けられませんが、営業日数に制限はありません。
2.物件を探す
賃貸または購入物件を見つけ、民泊として利用可能な物件かどうかを確認することが重要です。
物件を探す際には、転貸の許可が出ていることや家主が民泊の運営を許可していること、管理規約で民泊が許可されていることなどをチェックしておきましょう。
物件には、マンションや一戸建て、アパートなど、さまざまな選択肢があるため、ゲストが過ごしやすい物件の状態や設備であるかどうかを意識しながら物件を探すことが大切です。
3.事前相談に行く
民泊の許可申請を進める前に、一度保健所に相談に行きましょう。事前相談を通じて、地域特有の規制や要件を把握することができ、申請の際のトラブルを未然に防ぐことができます。運営予定の物件の所在地や営業形態、想定する宿泊客の数など具体的な話をしましょう。
また、地域によっては特別な条例や規制が存在する場合もあるため、事前に情報を収集しておくことが大切です。
4.必要な消防設備を設置する
物件が消防法に基づく安全基準を満たしているかを注意しましょう。各部屋への火災報知や各階への消火器の設置、避難経路指示などの確認が必要になります。
消防設備の設置にかかるコストは物件の規模にもよりますが、20~30万円程度の費用がかかります。設置が完了したら、消防署から消防法令適合通知書を発行してもらいましょう。
5.申請・届出に必要な書類を準備する
民泊の許可申請や届出を行う前に、必要な書類を準備します。申請者の本人確認書類として、運転免許証やパスポートなどの身分証明書、賃貸契約書などが必要です。
記入漏れがあると届出に時間がかかるため、忘れている書類がないか確認しながら進めていきましょう。
6.届出もしくは申請を行う
民泊を運営するためには、必要な書類を整えた後、実際に届出または申請を行うステップが重要です。
民泊新法の場合
- 所定の窓口に必要書類を提出します。
- 行政機関による審査が行われ、問題がなければ届出が受理されます。
旅館業法の場合
- 所定の窓口で詳細な書類を提出します。
- 保健所や消防署などの関係機関による検査が行われ、基準を満たしているかが確認されます。
手続きは、地域によって異なる場合があるため、事前に確認しておくことが重要です。
7.保健所の検査を受ける
届出を行うと、保健所が施設の検査を行います。主に施設内の清掃状態や衛生管理、設備の適切な配置などがチェックされます。
検査を受ける前には、施設の間取り図や衛生管理計画書などを事前準備しておきましょう。また、保健所の検査は地域によって異なる場合があるため、事前に地元の保健所に確認しておくことが大切です。
8.運営をスタートする
民泊の全ての許可申請が終わって検査に通れば、いよいよ運営スタートです。ゲストを迎えるために物件の清掃や必要なアメニティの用意、そして宿泊施設としての魅力を高めるための工夫が求められます。
また、ゲストとのコミュニケーションも重要になるため、予約管理やチェックイン・チェックアウトの手続き、さらには滞在中のサポートをスムーズに行うための体制を整えておくことが大切です。
民泊の許可申請や届出を行う前に必ず確認すること
民泊の届出を出す前に、記入漏れや見落としがないようにひとつずつ確認しておきましょう。申請に漏れがあると申請ができない可能性もあるため、注意が必要です。
居住要件と設備要件を満たしているか
民泊を運営するには、居住要件と設備要件のふたつを満たしていることが大切です。居住要件は、生活の本拠として使用されていることや入居者の募集が行われていることなどの条件に当てはまる必要があります。
一方、設備要件は、宿泊客が快適に過ごせるための最低限の設備が整っているかどうかです。トイレや浴室、キッチンなどの基本的な設備が完備されていることが求められます。
居住要件と設備要件については、民泊制度ポータルサイトをご確認ください。
転貸の許可とマンションの管理規約
民泊は通常、賃貸とは異なり第3者に物件を貸し出すため、物件の所有者から転貸の許可を得ることが不可欠です。
マンションなどの集合住宅では、管理規約に転貸に関する規定が設けられていることが多いため、事前に確認することが重要です。
管理規約によっては、転貸を禁止している場合や特定の条件を満たす必要がある場合があります。物件を選ぶ際には、管理規約をしっかりと読み込み、転貸が許可の有無があるかを確認し、管理組合に相談しましょう。
各地域の上乗せ条例
民泊新法や旅館業法だけでなく、地域ごとの上乗せ条例にも注意が必要です。上乗せ条例とは、国の法律に加えて、各地方自治体が独自に定める規制や条件のことを言います。
各地域の条例により民泊の運営に関するルールが地域ごとに異なるため、事前確認が重要です。例えば、ある地域では特定のエリアでの営業が禁止されていたり週末は営業できなかったりする場合があります。
条例を無視すると、罰則や営業停止のリスクがあるため、必ず調査し遵守することが求められます。地域の上乗せ条例については、各自治体の公式ウェブサイトや窓口で確認しましょう。
民泊新法の届出で必要になる書類
民泊新法に基づく届出を行う際には、以下の必要書類が必要です。
- 届出書
- 未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
- 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
- 住宅の登記事項証明書
- 「入居者の募集が行われている家屋」を証明する書類
- 「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」を証明する書類
- 住宅の図面
- 賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類
- 転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類
- 区分所有の建物の場合、規約の写し
- 管理組合に禁止する意思がないことを証する書類
- 委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し
これらの書類は、民泊を運営するための法的な要件を満たすために不可欠です。
届出書では、都道府県や市区町村の担当窓口で、物件の所在地や運営者の情報、運営計画などを提出します。民泊を運営する旨を正式に申請するための書類であり、所定のフォーマットに従って記入する必要があります。
全ての書類を整えることで、民泊新法に基づく届出がスムーズに進められるため、事前に必要な書類を確認して準備を進めることが重要です。
まとめ
民泊の許可申請は、事前の確認事項や必要書類をしっかりと把握することが重要であることがわかりました。
営業形態の選定から物件探し、消防設備の設置、そして申請手続きに至るまで、各ステップを丁寧に進めることでスムーズな運営が可能になります。
また、地域ごとの条例や居住要件、転貸の許可についても確認を怠らないでください。全ての準備を整えて、民泊事業をスタートさせましょう。
下記、行政書士費用の見積もりをチャットボットが自動で提示してくれる便利なサイトです。自動車、建設業、不動産、産廃、古物商、旅館・民泊、法人設立、NPO法人、相続手続き、補助金申請その他あらゆる行政手続きに対応しています。東京大学の工学修士であるDXに強い岡高志 行政書士が中心となり運営しています。