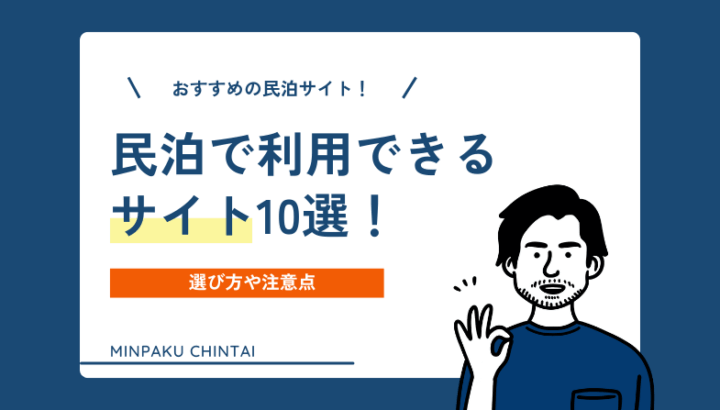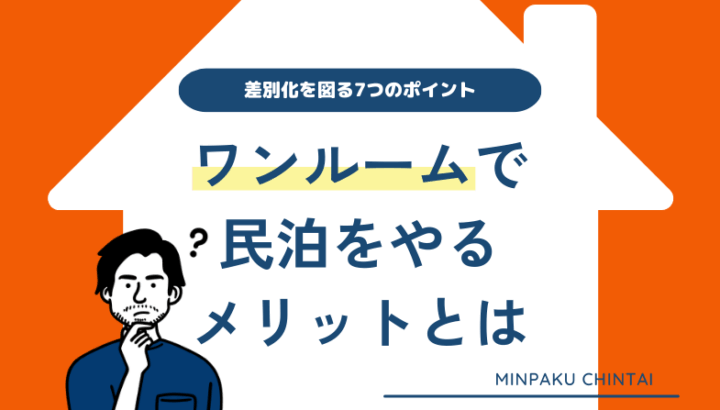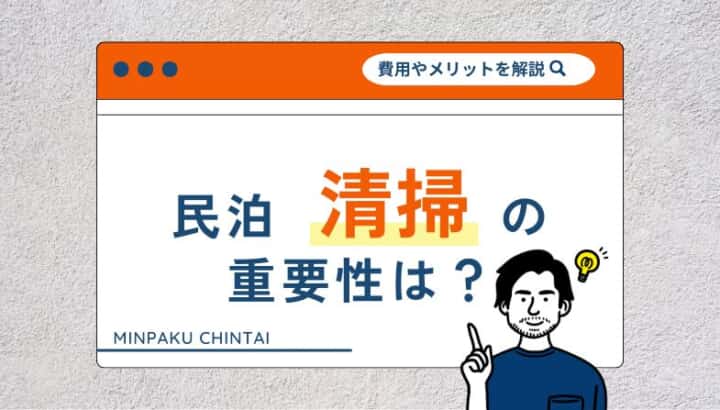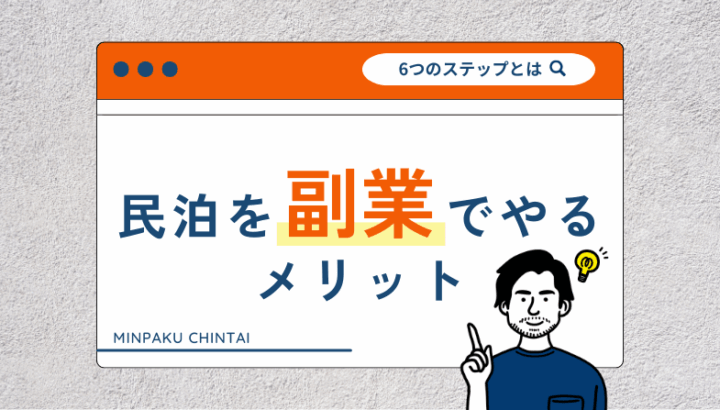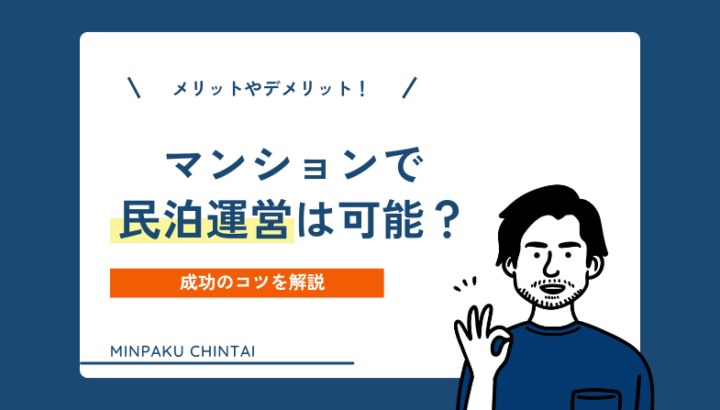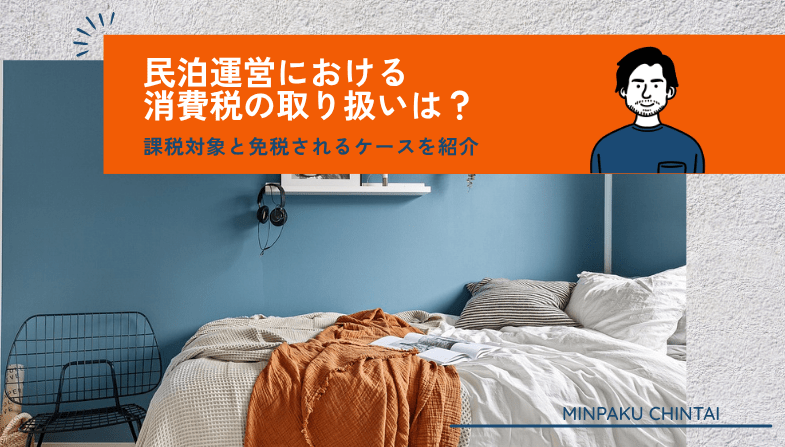
民泊運営における消費税の取り扱いは?課税対象と免税されるケースを紹介
民泊を運営していると、宿泊料などの収入に対して「消費税はどうなるの?」と疑問に感じたことはありませんか?
民泊における消費税の取り扱いは少し複雑で、課税対象となるケースと免税されるケースの両方があります。適切に理解しておかないと、思わぬ税負担が発生することも。
この記事では、民泊運営者が知っておくべき消費税の基本的な仕組みから、課税・免税の具体的な判断ポイントまでをわかりやすく解説します。正しい知識を身につけて、安心・適正な民泊運営を目指しましょう。
CONTENTS
民泊運営は消費税が課税される

民泊運営による収入は、原則として消費税の課税対象です。宿泊料をはじめとするサービス提供に伴う対価は「事業としての対価の提供」と見なされ、消費税法に基づき課税されます。
たとえば、AirbnbやBooking.comなどのプラットフォームを通じて宿泊者から料金を受け取る場合、その金額が課税売上に該当するということです。
民泊運営で消費税が課税されるもの

ここからは、民泊運営で消費税が課税されるものについて紹介します。
宿泊料金
民泊で得られる最も基本的な収入は宿泊料金です。この宿泊料金は、消費税法上「役務の提供」とされ、明確に課税対象とされています。
また、プラットフォームを介して料金を受け取る際、表示価格に消費税が含まれているかどうかを明確にしておくことが重要です。これはゲストとのトラブルを防ぐだけでなく、自身の税務処理においても正確に売上と消費税額を把握する必要があるためです。
さらに、長期滞在(1か月以上)の契約になると、居住用としての取り扱いになり非課税扱いになることもあるため、契約形態にも注意を払いましょう。
アメニティ
民泊ではシャンプーや歯ブラシ、タオルなどのアメニティを提供することが一般的ですが、これらも課税の対象になる場合があります。
特に、宿泊料金とは別に「アメニティ代」や「リネン使用料」などの名目で追加料金を徴収している場合は、それが物品の販売またはサービス提供と見なされ、消費税が課されます。
一方で宿泊料にこれらのコストを包括している場合には、まとめて課税対象となります。つまり、アメニティを有償で提供しているかどうか、またその提供方法によって課税判断が変わるということです。
付帯サービス
清掃サービスやチェックインサポート、荷物の預かり、レンタル自転車の提供など民泊運営には多くの付帯サービスが関わっています。
これらのサービスも、宿泊とは別個に料金を設定して提供している場合、消費税の課税対象になります。たとえば、「チェックアウト後の荷物預かり1回500円」などと明記している場合、その金額に対して消費税を計上しなければいけません。
また、委託している清掃業者への支払いにも消費税が発生するため、受け取る側・支払う側の両面で課税取引となる点にも注意が必要です。
民泊運営で消費税が免税になるケース

ここからは、民泊運営で消費税が免税になるケースについて紹介します。
課税売上高が1千万円以下
消費税法では、基準期間(原則として2期前の課税期間)における課税売上高が1,000万円以下である場合、その事業者は「免税事業者」として扱われ、消費税の納税義務が免除されます。
たとえば、2025年の消費税納税義務を判断する際には、2023年の課税売上高が1,000万円を超えていたかどうかが基準になります。この制度は、開業間もない事業者や個人で小規模に運営している民泊オーナーにとって非常に有利に働くものです。
ただし、2023年10月に始まったインボイス制度の影響により、たとえ免税事業者であっても取引先からインボイス発行を求められ、結果的に課税事業者へと変更を余儀なくされるケースが増えています。
つまり、売上規模だけでなく、今後のビジネス方針や取引先との関係性も考慮して、免税を続けるかどうかの判断を慎重に行う必要があります。
1ヵ月以上の貸し付けを行っている
民泊においては、貸し出す期間によっても消費税の取り扱いが異なります。具体的には、1ヵ月(30日)以上の継続的な賃貸契約を結んでいる場合、その取引は「住宅の貸付け」とみなされ、消費税が非課税となります。
これはホテルや旅館などの一時的な宿泊とは異なり、住宅としての性質を持つ契約と判断されるためです。たとえば、転勤者や留学生向けに長期滞在用として部屋を貸している場合、その収入に対しては消費税が課されません。
ただし、契約期間が31日であっても、実態として短期滞在を繰り返しているような場合には課税対象と見なされるリスクもあるため、契約内容や運営実態をしっかり記録しておくことが重要です。長期貸しの方が安定した収入と非課税のメリットを両立できる点で、民泊の収益モデルとして検討する価値は十分にあります。
消費税の計算方法

民泊運営者が課税事業者である場合、消費税の納付額は「課税売上に対する消費税」から「課税仕入れに対する消費税」を差し引いた金額で算出されます。
たとえば、宿泊料や有料サービスで得た収入が年間で800万円(税抜)あり、仕入れや外注費などに300万円(税抜)の経費がかかった場合、消費税はまず売上に対する税(800万円 × 10% = 80万円)から、仕入れにかかる税(300万円 × 10% = 30万円)を差し引き、差額の50万円が納付すべき税額となります。
このように「仕入税額控除」により実際の納付額が軽減される制度があり、領収書や請求書の管理が非常に重要になります。
なお、2023年から始まったインボイス制度により、仕入税額控除を適用するためには「適格請求書(インボイス)」の保存が必須となりました。民泊事業者としても、自身がインボイス発行事業者かどうか、取引先が発行しているかどうかを確認しながら、正確に消費税を計算・申告することが求められます。
民泊の運営者は「簡易課税制度」が利用できる

課税事業者として消費税を納めることになった場合でも、すべての事業者が複雑な消費税計算を行う必要はありません。年間の課税売上高が5,000万円以下の中小事業者は「簡易課税制度」を選択することができます。
これは、実際の仕入れにかかる消費税額をもとに計算するのではなく、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を用いて簡易的に納税額を算出する制度です。たとえば、民泊運営は「サービス業」として扱われることが一般的であり、この場合、みなし仕入率は50%とされます。
つまり、課税売上の半分に相当する金額に対してのみ消費税が課されるため、記帳や領収書の整理にかかる手間を大きく削減することができます。ただし、一度簡易課税を選択すると2年間は変更できない点や、仕入れ控除を受けられないことで損をする場合もあるため、適用前には慎重な試算が必要です。
海外民泊サイトの手数料は「リバースチャージ」対象

AirbnbやBooking.comなど、海外に拠点を置く民泊仲介サイトを利用している場合、プラットフォームから請求される手数料については「リバースチャージ制度」が適用されます。
これは、海外事業者から役務提供を受けた場合に、国内の事業者側が本来の納税義務を負うという仕組みです。たとえば、Airbnbからサービス料として3,000円を請求された場合、通常の国内取引と異なり、民泊運営者自身が3,000円にかかる消費税(300円相当)を国に納付する義務が発生します。
免税事業者であればこの制度は適用されませんが、課税事業者であれば必ず対応しなければならず、インボイス制度の導入に伴い税務リスクも高まっています。
特に、会計ソフトによる自動処理がうまくいかないケースや、請求書が海外表記でわかりづらい場合もあるため、リバースチャージ対象の支出は別途きちんと管理することが重要です。
消費税を考慮して民泊運営しよう
民泊を継続的に運営するときは、単に集客やレビュー対応だけでなく、税金への理解と対策が非常に重要です。特に消費税に関しては、売上規模や提供サービスの内容、契約期間、利用するプラットフォームの種類など、さまざまな要因によって課税・免税の区分が変わってきます。
そのため、消費税の仕組みを正しく理解し、自身の運営スタイルに最適な制度や対策を選択するよう心がけましょう。少しでも不安がある場合は、早めに税理士などの専門家に相談することをおすすめします。