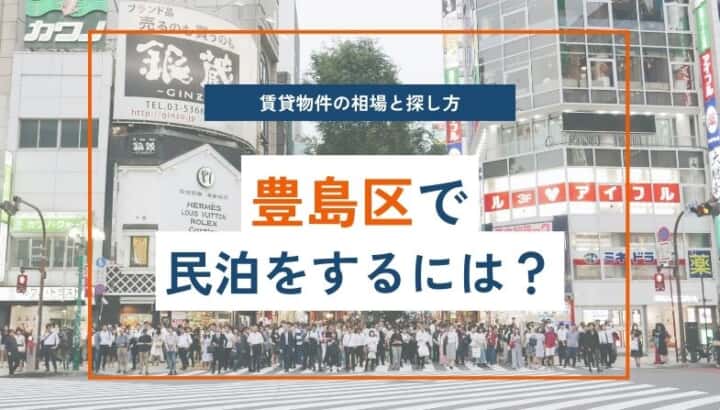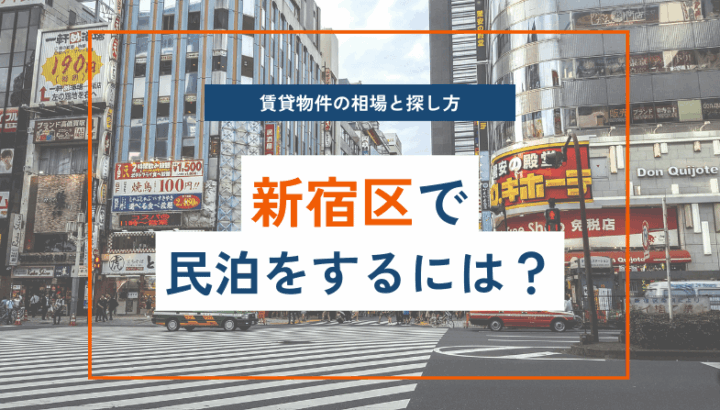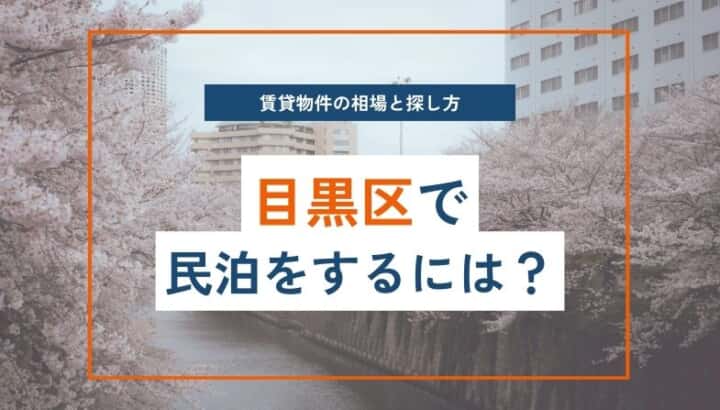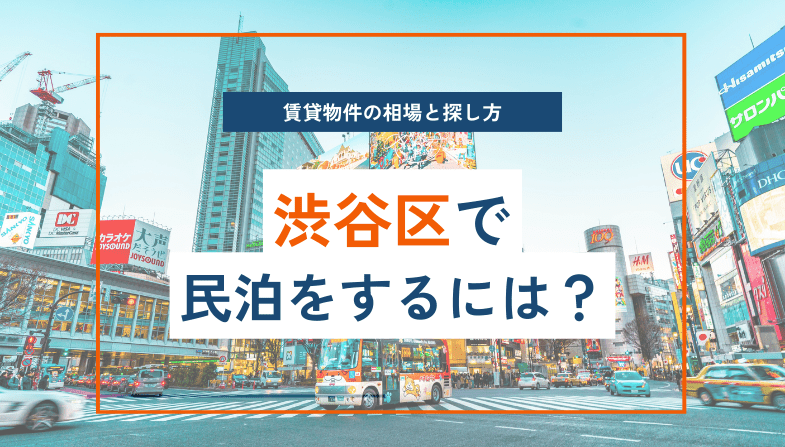
【渋谷区編】賃貸物件で民泊をする際の相場と物件の探し方
渋谷区は観光客やビジネスパーソンに人気のエリアで、民泊は魅力的なビジネスチャンスになるでしょう。しかし、成功するためには、渋谷区の家賃相場や民泊市場の動向を理解することが重要です。
そこで今回は、渋谷区の家賃の相場や平均稼働率などの民泊市場のデータをご紹介します。物件選びや料金設定にぜひ活用してみてください。
CONTENTS
賃貸物件で民泊はできるのか
賃貸物件での民泊は転貸とみなされるため、オーナーからの転貸許可が必要です。許可なしに運営すると契約違反となり、運営ができなくなる可能性もあるので気を付けましょう。
物件を探す際には、オーナーに転貸と民泊の運営も可能かどうかを確認することが大切です。
また、近年は民泊ができる賃貸物件を探せるサイトが増えてきているため、民泊可能物件から探してみるのもおすすめです。
転貸と民泊について詳しく知りたい方には、こちらの記事もおすすめです。
関連記事:転貸物件で民泊をするときに必要な手続きや運営のポイント
渋谷区で民泊を始める際に知っておきたいこと
渋谷区で民泊を始めたい人は、以下の2点について知っておきましょう。
- 上乗せ条例
- 届出の手順
地域の条例や届出の方法については、あらかじめ把握しておくことで準備がスムーズに進みます。
上乗せ条例
渋谷区では、文京地区と住居専用地域では、民泊を営業できる期間が決まっています。
制限地域では、以下の期間は稼働できないので注意しましょう。
- 4月5日 ~ 7月20日
- 8月29日 ~ 10月第2月曜日前週の水曜日
- 10月第2月曜日前週の土曜日 ~ 12月25日
- 1月7日 ~ 3月25日
ただし、制限地域であっても、以下の条件を満たして近隣住民からの苦情に適切に対応できると認められた場合、180日以内の民泊が許可されることがあります。
- 時間帯を問わずに連絡が取れる人員が確保できていること
- 緊急事態の場合に、おおむね10分以内に駆けつけられる人員がいること
- 苦情の内容や対応についての記録を保存していること
届出の手順
渋谷区で民泊を始める際には、民泊新法での届出を行います。
まずは、物件が居住要件や設備要件を満たしているかを確認しましょう。制限区域に当てはまらないか、マンションの管理規約や転貸に関する契約確認も必須です。
事前周知については、届出をする7日前までに行うよう定められています。必要な書類を集めて届出が完了すれば、標識を受け取って運営が開始できます。
運営開始後も定期的に報告を行う必要があるため、しっかりとした管理体制を整えることが大切です。詳しい届出の方法については、渋谷区のHPをご確認ください。
また、こちらの記事でも必要書類について解説しています。
関連記事:民泊の許可申請のやり方を解説!事前の確認事項と必要書類は?
渋谷区の賃貸相場
渋谷区の家賃相場は、23区の中でも高めです。
| ワンルーム | 12万円 |
| 1K | 11.9万円 |
| 1DK | 17万円 |
| 1LDK | 22万円 |
では、移動に便利な主要駅の周辺の相場も見てみましょう。
| 渋谷駅 | ワンルーム:14万円1K:13万円 |
| 原宿駅 | ワンルーム:16万円1K:13万円 |
| 恵比寿駅 | ワンルーム:13万円1K:14万円 |
| 代々木駅 | ワンルーム:12万円1K:12万円 |
| 代官山駅 | ワンルーム:14万円1K:14万円 |
ワンルームでも13万円前後と、高いことがわかります。
経費の中で家賃が占める割合が多くなるため、最終的に黒字になるかどうかのシミュレーションが欠かせません。稼働率をもっと上げたいと考えている方は、旅館業も検討してみると良いでしょう。
渋谷区の民泊市場
渋谷区は観光地としての魅力が高く、多くの旅行者が集まるエリアです。
そのため、民泊市場も非常に活発で、特に近年の訪日外国人の増加に伴い需要が高まっています。
(データ元:AirDNA)
| 平均稼働率 | 平均宿泊単価 | 物件数 |
| 81% | 19,900円 | 519 |
平均稼働率は81%と非常に高く、常に人気のエリアであることがわかります。
観光スポットや大型のショッピングエリアも多いため、ゲストにとっては利便性が高いのがメリットです。
渋谷区の民泊可能な賃貸物件の探し方
渋谷区で民泊ができる賃貸物件を探す際は、不動産サイトや民泊専用のプラットフォームを活用できます。
不動産サイトで気になった物件があれば、直接問い合わせて民泊ができるか確認してみましょう。
ただ、賃貸物件は民泊NGなところも多いため、効率良く物件探しをしたい場合は民泊ができる物件を紹介しているサイトの利用がおすすめです。
また、地元の不動産業者に相談して物件の紹介を依頼すると、民泊に適した物件を紹介してくれる可能性があります。
物件の探し方については、こちらの記事を参考にしてみてください。
関連記事:民泊の許可申請のやり方を解説!事前の確認事項と必要書類は?
まとめ
渋谷区での賃貸物件を使った民泊は、魅力的なビジネスチャンスですが、地域の条例の理解や適切な届出を行うことが大切です。
家賃相場が高いエリアなので、家賃やアメニティなどにかかる経費を回収できるか、利益を出せるかなども合わせて慎重に考えてみましょう。
宿泊料金を設定する際は、平均宿泊単価も参考にしてみてください。本記事のポイントを踏まえて、渋谷区での民泊事業の成功に向けた準備を進めていきましょう。