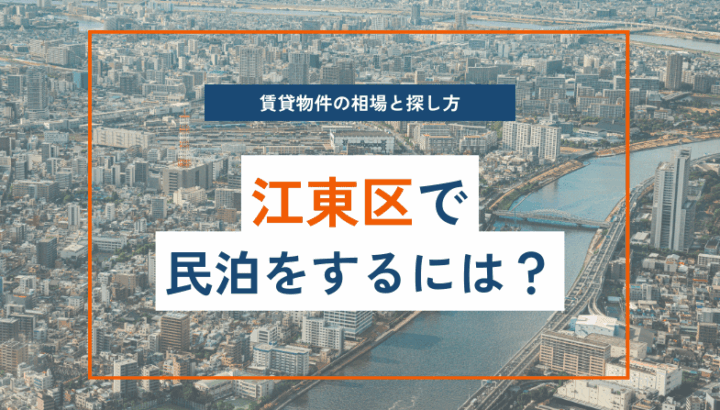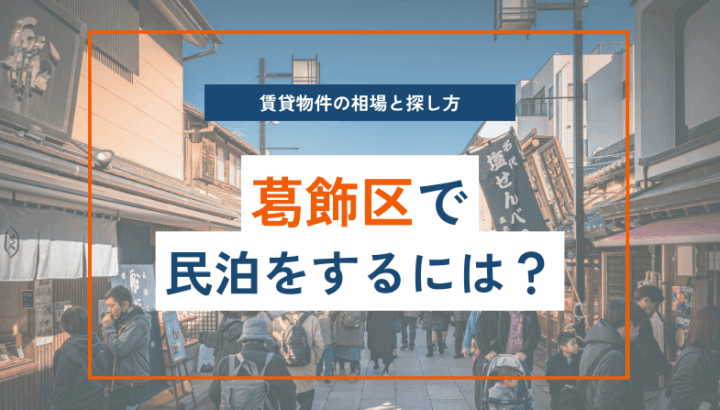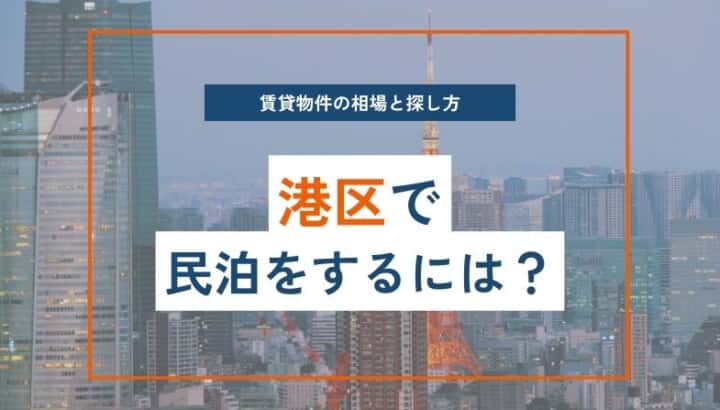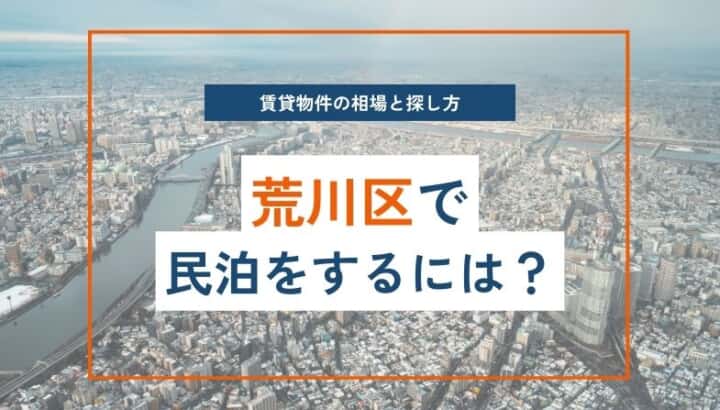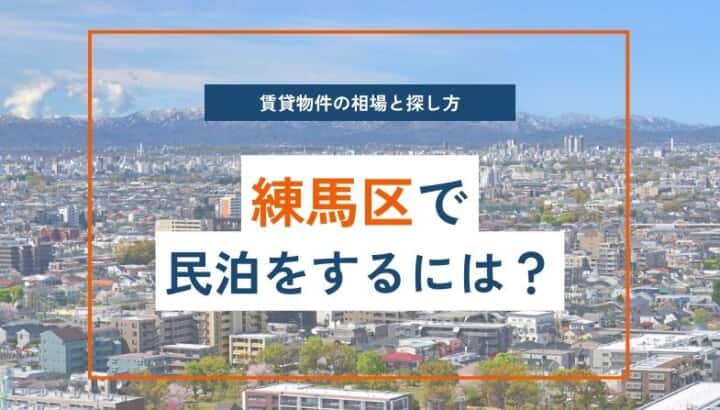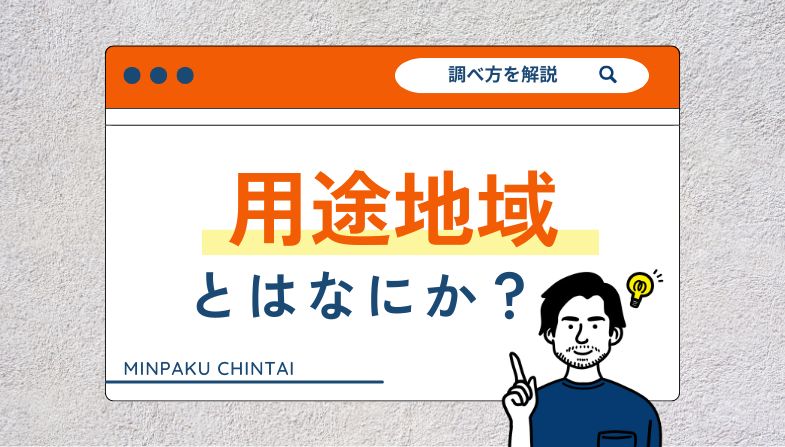
用途地域とは?民泊運営が可能な用途地域と調べ方を解説
民泊を始めたいと思ったとき、まず確認すべきポイントのひとつが「用途地域」です。用途地域とは、建物の建て方や使い方を制限することで、住みやすい街づくりを目指すために定められた都市計画上の区分です。
本記事では、そもそも用途地域とは何か、民泊運営が可能な用途地域の種類、そして具体的な調べ方までをわかりやすく解説します。民泊を安心・安全に始めるための第一歩として、ぜひご覧ください。
CONTENTS
用途地域とは

用途地域とは、都市計画法に基づいて都市の健全な発展と住環境の保護を目的に定められる地域区分のことです。住居系・商業系・工業系の3つの大分類と、それに属する13の細分類があり、地域ごとに建築できる建物の種類や用途に制限が設けられています。
例えば、静かな住環境を維持したい住宅地では、騒音や交通量が多くなる商業施設や工場の建設が制限されます。このように、用途地域は都市における土地利用のルールを定め、住民の安全や快適性を守る重要な制度です。民泊を運営するうえでも、この用途地域の区分は大きな影響を与えるため、事前に確認しておくことが欠かせません。
民泊運営が可能な用途地域

ここからは、民泊運営が可能な用途地域について紹介します。
旅館業法における用途地域
旅館業法に基づく民泊、いわゆる「簡易宿所」として運営できる用途地域は、以下のとおりです。
・第一種住居地域(3000㎡以下)
・第二種住居地域
・準住居地域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域などの、住環境の静けさや安全性を重視したエリアでは営業許可が下りません。住居系の地域でも特定の条件を満たせば営業可能なケースがありますが、自治体ごとに細かな規制やガイドラインが異なるため、事前に保健所などと十分に協議を行うことが重要です。
建築基準法によって建物の用途変更が必要な場合もあり、見落とすと営業停止に繋がるリスクもあります。
住宅宿泊事業法における用途地域
住宅宿泊事業法で運営できる用途地域は、以下のとおりです。
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・田園住居地域
・近隣商業地域
・商業地域
・工業地域
・準工業地域
住宅宿泊事業法、いわゆる「民泊新法」に基づく民泊は、旅館業法と比べると用途地域の制限が緩やかです。この法律では、原則としてすべての用途地域において民泊の届け出が可能とされています。これは、あくまでも「住宅」であることが前提であり、施設の主たる用途が住居であることが条件です。
そのため、住宅地に建つ戸建てや分譲マンションの一室でも、一定の条件を満たせば合法的に民泊運営を行うことが可能です。ただし、自治体によっては独自の条例を制定し、住宅宿泊事業の実施を制限しているケースも多く存在します。
特に住居専用地域では住民の反対や地域トラブルを避けるために、営業日数の制限や事前説明義務などが課されることがあります。用途地域に加え、自治体のルールを確認することが極めて重要です。
特区民泊における用途地域
特区民泊で民泊が可能な用途地域は、以下のとおりです。
・大田区
・千葉市
・新潟市
・大阪府
・大阪市
・八尾市
・北九州市
・寝屋川市
国家戦略特区制度を活用した「特区民泊」は、都市の競争力強化を目的とする政策の一環として、地域限定で導入されています。
東京の大田区などで実施されており、民泊新法や旅館業法とは異なる独自のルールが適用されます。多くの自治体では、住居専用地域も含めて比較的広範な用途地域での民泊が認められており、これによって事業の自由度が高まっています。
ただし、施設の構造や管理体制に対しては厳しい基準が設けられており、例えば24時間対応の管理者の設置や外国人旅行者への対応マニュアルの整備などが求められます。さらに、地域住民への説明責任や苦情対応体制の構築も重要視されるため、単に用途地域の制限が緩いからといって簡単に開業できるわけではありません。特区民泊は、用途地域の制限をクリアしつつ、しっかりとした運営体制を整えることが成功の鍵を握っています。
用途地域を調べる方法

ここからは、用途地域を調べる方法について紹介します。
用途地域マップを利用する
メタウェアリサーチ有限会社が公開している「用途地域マップ」を利用すれば、用途地域はを確認できます。用途地域マップは自治体や省庁が公開しているオープンデータを利用しているので、用途区分を正確に把握することができます。
また、第一種住居地域や商業地域などの区分が色分けされて表示されているため、誰でも簡単に確認できるのが特徴です。また、建ぺい率や容積率、さらに建築基準法上の制限もあわせて掲載されていることが多く、民泊以外の用途検討時にも有用です。
更新頻度も比較的高く、制度変更や再開発に伴う用途変更が反映されるため、最新情報の確認には欠かせません。
参照:用途地域マップ
検索エンジンで調べる
用途地域について手軽に知りたい場合は、インターネット検索エンジンを活用する方法も有効です。「〇〇市 用途地域 地図」などのキーワードを入力すれば、該当地域の用途地域を確認できる可能性が高まります。
また、用途地域に関する専門サイトや不動産関連のブログ、解説記事なども多く公開されており、基本的な制度理解に役立つでしょう。
ただし、非公式の情報には古い内容や誤った記述も含まれていることがあるため、必ず一次情報である自治体のページに戻って確認する習慣を持つことが大切です。検索結果を鵜呑みにせず、情報の正確性を見極めることが求められます。
自治体に問い合わせする
より確実に用途地域を確認したい場合や、特殊なケースについて知りたい場合は、自治体の都市計画課などに直接問い合わせるのがおすすめです。
市役所や区役所の窓口での相談を通じて、該当地の正確な用途区分や民泊に対する制限の有無などを確認することができます。特に自治体ごとに条例や運用方針が異なる民泊制度では、現場の担当者の見解を得ることがトラブルを防ぐ鍵となるでしょう。
たとえば、「住宅宿泊事業法に基づく届出は可能だが、地域独自の制限がある」といったケースも多く、紙面だけでは読み取れない実務上のポイントを知ることができます。時間や手間はかかりますが、将来的なトラブルを避けるためには非常に有効な手段です。
用途地域に関するポイント・注意点

ここからは、用途地域に関するポイント・注意点について紹介します。
特別用途地区に該当するケースがある
用途地域が同じであっても、特定の地域においては「特別用途地区」に指定されていることがあります。これは通常の用途地域の枠組みに加えて、さらなる制限やルールを加えるもので、例えば文教地区や風致地区、景観地区などがそれに該当します。
これらの地域では、教育機関の静謐な環境を守るためや自然景観を保全するために、民泊のような不特定多数の出入りを伴う事業に制限がかかることがあります。用途地域だけで判断せず、その地域が特別用途地区に指定されていないかも合わせて確認しましょう。
自治体の条例によって民泊の運営期間が制限される
住宅宿泊事業法に基づく民泊では、年間の営業日数が180日以内と法律で定められていますが、実際には各自治体がさらに厳しい独自条例を設けている場合があります。たとえば、地域の住民とのトラブル防止や騒音対策の観点から、民泊の営業を特定の曜日や季節に限定する措置をとっている自治体もあります。
こうした条例は、同じ用途地域内でもエリアごとに異なる適用がなされることが多く、表面上の法律だけを鵜呑みにすると「届け出は受理されたが、実際には営業できない」といった事態に陥ることもあります。
そのため、民泊を開始する前には、条例レベルでの詳細な規制内容を確認し、カレンダー上で営業可能な日数や方法をシミュレーションしておくことが極めて重要です。
法的な悩みは行政書士や弁護士に相談が必要

用途地域や条例の内容は複雑かつ専門性が高いため、自力での解釈や判断に限界がある場合があります。特に旅館業法や民泊新法、建築基準法などが絡み合うケースでは、正確な手続きを踏まないと営業停止や罰則の対象となるリスクがあります。
こうした事態を避けるためには、行政書士や弁護士といった法律の専門家に相談することが非常に有効です。行政書士は主に書類作成や届出手続きの代行を行い、弁護士はトラブル対応や契約書のチェックなどに強みを持っています。実際の運営に入る前に、専門家と連携してリスクの洗い出しを行い、法的に安全な枠組みの中で民泊事業を進めることが、長期的な成功に繋がります。
用途地域を守って民泊運営しよう
民泊の運営は、ただ物件を貸し出せば成立するものではありません。特に都市部や住宅街では、用途地域や地域条例といったルールをしっかり守ることが前提となります。これを無視して営業を行うと、近隣住民とのトラブルや行政からの指導・営業停止といった重大なリスクに直面することになります。
逆に、法令や地域のルールを順守しながら運営すれば、地域との良好な関係を築きつつ、安定した収益を見込める民泊運営が可能になるでしょう。法的な確認や地域への配慮を怠らず、誠実な姿勢で運営に臨むことが、成功する民泊事業者に共通するポイントです。