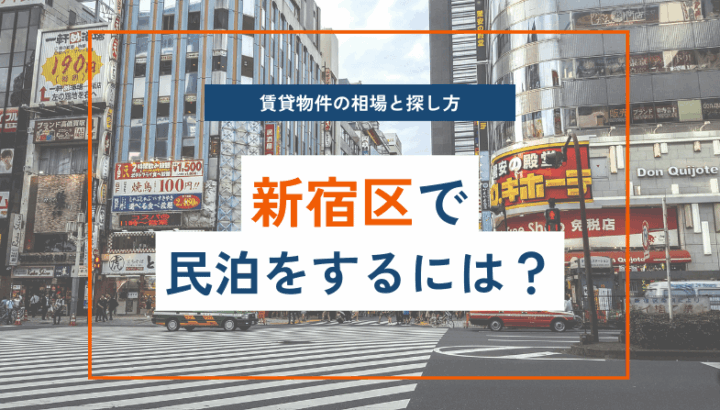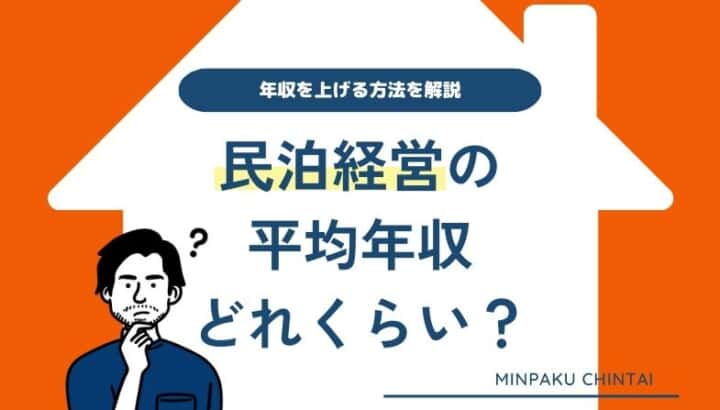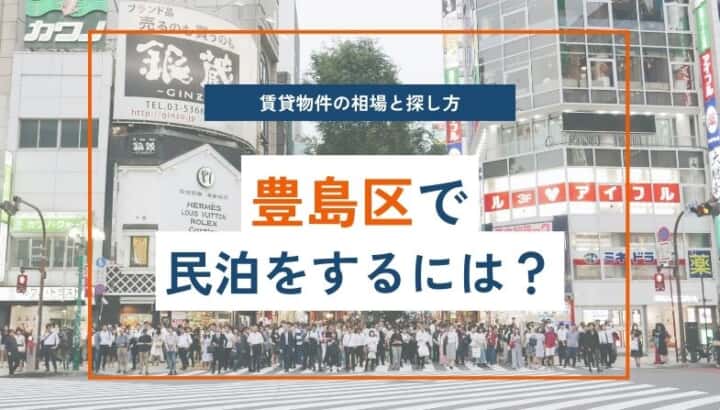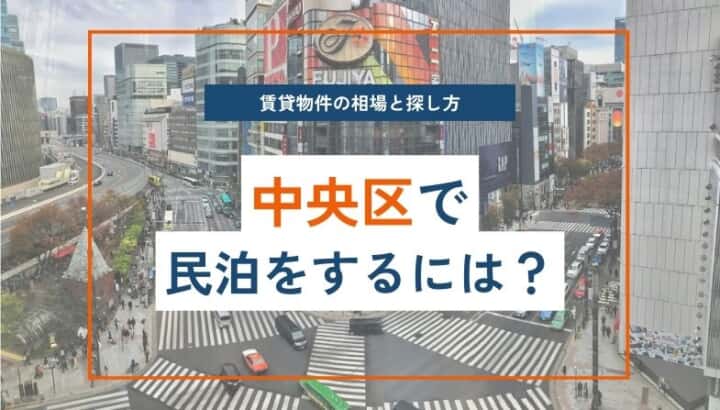民泊における規制内容は?規制背景や義務、運営に関わる法律を解説
民泊は、観光業の発展や空き家対策の一環として注目を集めている一方で、近隣トラブルや無許可営業といった問題も多く、法規制の対象となっています。民泊を適法に運営するには、旅館業法や住宅宿泊事業法(民泊新法)など、関係する法律や自治体ごとのルールを正しく理解することが不可欠です。
この記事では、民泊に関わる主な規制内容やその背景、オーナーが守るべき義務や手続きについて解説します。これから民泊を始めたい方はぜひご覧ください。
CONTENTS
民泊運営における規制内容は?

ここからは、民泊運営における規制内容について紹介します。
年間営業日数に上限がある
住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく民泊運営では、年間営業日数の上限が180日と定められています。これは、あくまで住宅を活用した宿泊事業という前提での制度設計であり、年間を通じてフル稼働するホテルや旅館とは異なる点に注意が必要です。
この「180日」という制限はカレンダー通年で計算されるため、繁忙期のみに集中して営業するなど、戦略的な運営が求められます。また、営業日数のカウントはゲストが宿泊した日を基準とするため、予約が入っていない日はカウントに含まれません。
違反があった場合には行政指導や業務停止の対象となるため、営業日数の管理には注意を払いましょう。
最低宿泊日数が設定されている
地域や条例によって、定められている最低宿泊日数が異なります。都市部の一部では1泊2日の短期利用によるトラブル防止を目的に2泊以上、あるいは37泊以上といった最低宿泊日数の制限を課しているケースもあります。
実際、東京都大田区で特区民泊を行う場合は、最低宿泊日数が「2泊3日以上」に設定されています。
そのため、物件を民泊として活用する際には、所在地の自治体が定める条例や特区の規則を事前に確認し、必要に応じて運営ルールを調整する必要があるでしょう。
運営方法によっては管理業者への委託が必要
民泊を運営するにあたって、届け出た物件が「管理不在型」である場合、国土交通省に登録された住宅宿泊管理業者への委託が法律で義務付けられています。これは、オーナーが物件の近くに居住していない、または常時管理できない状況下で、ゲスト対応やトラブル時の連絡体制を整えるための制度です。
管理業者は宿泊者との連絡や鍵の受け渡し、緊急時の対応、近隣住民への配慮に至るまで、幅広い業務を代行する役割を担っています。自身で運営する場合と比較して運用コストはかかりますが、トラブル防止や法令遵守の観点からも、管理業者の存在は非常に重要です。
自治体による規制
民泊の運営には国の法律だけでなく、各自治体が定める独自のルールや条例も大きく関わってきます。各自治体による規制は、地域住民との共存や騒音・ゴミ出しといった生活環境の維持を目的としており、無視して運営した場合には指導や罰則の対象となる可能性があります。
また、自治体によっては特区民泊制度や認定制度を導入し、より柔軟に民泊を運用できる仕組みを整えているところもあるため、運営を始める前に必ず地域の最新情報を確認することが求められます。
民泊運営におけるオーナーの義務

宿泊者名簿の作成と保存
民泊オーナーには、宿泊者ごとの情報を記録する「宿泊者名簿」の作成と保存が法律で義務付けられています。これは、住宅宿泊事業法に基づいた重要な義務であり、以下のような情報を最低でも3年間保管しておく必要があります。
・宿泊者の氏名
・住所
・職業
・宿泊日
特に外国人旅行者を受け入れる場合には、旅券の写しを取得して保存することも求められており、本人確認を徹底する意味でも欠かせない対応です。宿泊者名簿の作成は、トラブル発生時の責任の所在を明確にしたり、行政による調査に協力するためにも重要な役割を果たします。
周辺住民に対する説明
民泊運営を開始するにあたり、周辺住民や管理組合への説明責任を果たすことも、オーナーとしての重要な義務の1つです。特に住宅宿泊事業法の届け出を行う場合には、事前に物件の周囲に住む住民へ書面で通知を行うことが義務付けられており、トラブルや苦情を未然に防ぐための配慮が求められます。
周辺住民にとって、知らない外国人や旅行者が頻繁に出入りするというのは、治安や騒音、ゴミ出しなどに対する不安要素になることもあるため、誠実な対応が不可欠です。自治体によっては説明会の開催や掲示板への告知を求められるケースもあり、信頼関係を築くためには丁寧な対応が運営の成功を左右します。
民泊という新しいサービスが地域に受け入れられるかどうかは、こうした日頃の近隣対応に大きくかかっていると言っても過言ではありません。
ゲストの安全の確保
民泊オーナーには、宿泊施設としての最低限の安全性を確保する責任があります。これは、単に清掃が行き届いているだけではなく、火災報知器や消火器の設置、避難経路の明示、鍵の管理、セキュリティ対策といった安全に関わるあらゆる要素を含みます。
住宅宿泊事業法では、安全・衛生上の管理体制を整えていることが求められ、特にゲストが海外からの訪問者である場合には、言語対応を含む案内表示の整備なども重要となります。
また、事故や病気など緊急時に迅速に対応できる体制を整えておくことも必要であり、連絡先の掲示や緊急時の対応マニュアルなどを備えておくことが推奨されます。
民泊規制の背景

ここからは、民泊規制の背景について紹介します。
ホテル業界の保護
民泊規制が導入された背景の1つとして、ホテル・旅館業界の保護が挙げられます。民泊が急速に拡大したことで、従来の宿泊業者との競争が激化し、価格競争の激化や宿泊需要の分散が起こりました。
ホテルや旅館は、営業許可の取得や厳格な衛生管理、消防基準の遵守など、多くの規制をクリアした上で運営されています。
一方で、民泊は比較的簡単に運営できるため、ホテル業界との公平性が保たれないという指摘もありました。こうした状況を踏まえてできた規制が、前述した180日ルールです。
政府はホテル業界とのバランスを取るために、年間180日という営業日数の上限を設けることで、民泊の影響を一定程度抑えつつ、合法的な形での運営を促進する方針を取っています。
違法民泊の規制
民泊規制が設けられたもう1つの理由は、違法民泊の増加を抑制するためです。民泊市場が拡大するにつれて、無許可で営業する物件が増え、トラブルが多発するようになりました。
無許可の民泊は、宿泊者の安全性が確保されていなかったり、オーナーが十分な管理を行わなかったりすることが多く、行政としても問題視していました。
そのため、届出を行った物件のみが一定の条件のもとで民泊営業を行えるようにすることで、市場の健全化を図っています。
近隣トラブル対策
民泊の増加に伴い、近隣住民とのトラブルが社会問題化したことも民泊規制が導入された背景の1つです。民泊は、一般の住宅を宿泊施設として活用するため、居住者と宿泊者が同じ建物や地域に共存する形になります。
その結果、深夜の騒音やゴミ出しのルール違反、共用スペースの無断使用などの問題が多発しました。こうした近隣トラブルを抑えるために、民泊の営業日数を制限することで、年間を通じた影響を軽減し、地域との共存を促す狙いがあります。
民泊運営・規制に関わる法律

ここからは、民泊運営・規制に関わる法律について紹介します。
住宅宿泊事業法(民泊新法)
住宅宿泊事業法、通称「民泊新法」は2018年に施行された法律で、民泊運営を正式に制度化した枠組みです。この法律により、従来グレーゾーンとされていた一般住宅での宿泊サービス提供が、一定の条件を満たすことで合法的に行えるようになりました。
主な特徴としては、年間営業日数の上限が180日であること、宿泊者名簿の作成や住民への通知義務、適切な衛生管理や安全措置が求められることなどが挙げられます。さらに、物件の管理体制に応じて、住宅宿泊管理業者への委託が必要になる場合もあり、運営方法に応じた柔軟な対応が求められます。
この法律の導入により、個人オーナーでも一定のルールに則れば民泊運営が可能となった一方で、違反があった場合の罰則も明確に定められています。そのため、法令を十分に理解したうえで、正しい手続きを踏むことが、スムーズで持続可能な民泊運営の基本となります。
旅館業法
民泊運営に関するもう一つの重要な法律が「旅館業法」です。これは元々、ホテルや旅館といった宿泊施設の営業を規制するために制定された法律であり、民泊にも一定条件下で適用されることがあります。
特に住宅宿泊事業法ではなく、特区民泊や簡易宿所として運営する場合には、この旅館業法の許可が必要となります。旅館業法の許可を取得するには、消防法に基づく防火設備の設置や、一定の面積基準、設備要件を満たす必要があるため、一般の住宅をそのまま転用することは難しい場合があります。
また、保健所や建築基準法との整合性も求められ、自治体ごとに求められる基準にも違いがあるのが特徴です。旅館業法を選択することで、年間営業日数の制限を受けずに通年営業が可能になるというメリットがある一方、初期費用や手続きのハードルが高くなる傾向にあります。
民泊規制が緩和された理由

ここからは、民泊規制が緩和された理由について紹介します。
インバウンド需要への対応
民泊規制が緩和された背景の1つに、急増するインバウンド観光客の受け皿を確保する必要性がありました。特に2010年代後半から、日本を訪れる外国人観光客の数は右肩上がりに増加し、都市部を中心に宿泊施設の需要が急激に高まっています。
政府は観光立国を掲げ、訪日観光客数のさらなる拡大を目指していたものの、ホテルや旅館といった従来型の宿泊施設だけでは対応しきれないという現実がありました。そこで注目されたのが、個人が所有する住宅や空き家などを活用した「民泊」です。
これまで民泊は、旅館業法などの規制のもとでは違法性を指摘されるケースも多く、グレーゾーンに位置づけられていたのが実情です。しかし、住宅宿泊事業法(民泊新法)の制定により、一定のルールを設けたうえで個人による宿泊事業を合法的に認めることになり、より柔軟にインバウンド需要に対応できる体制が整えられました。
宿泊施設不足の解消
大規模なイベントや観光シーズンにおいて、日本国内では宿泊施設の絶対数が不足しているという課題が長年指摘されてきました。特に東京・大阪・京都などの観光都市では、旅行シーズンや大型連休になるとホテルが軒並み満室となり、宿泊料金の高騰や予約困難といった現象が頻発していました。
こうした問題を解決する手段として、既存の住宅を宿泊施設として有効活用できる民泊の制度化を推進しています。民泊は、空き家対策や都市部の狭小物件の有効活用にもつながる点が評価され、宿泊施設不足を補う「補完的な存在」として社会的にも受け入れられるようになってきました。
民泊規制を理解して民泊を始めよう
民泊は、個人でも始められる魅力的なビジネスである一方で、各種法令や条例に基づいた適切な運営が求められる分野です。近年、規制が緩和されたとはいえ、完全に自由に行えるわけではなく、住宅宿泊事業法をはじめとする関係法令をきちんと理解したうえで取り組む必要があります。
特に年間営業日数の制限や宿泊者名簿の作成、近隣住民への事前説明、安全対策などオーナーとして守らなければならない義務は多岐にわたります。
こうした規制を正しく理解し、適切な対応を講じることは、トラブル防止やゲスト満足度の向上につながるだけでなく、地域社会との良好な関係を築くうえでも不可欠な要素です。民泊を健全に運営するためには、法令を味方につける姿勢が何より重要であり、ルールを守りながら長期的かつ安定的な運営を目指していきましょう。