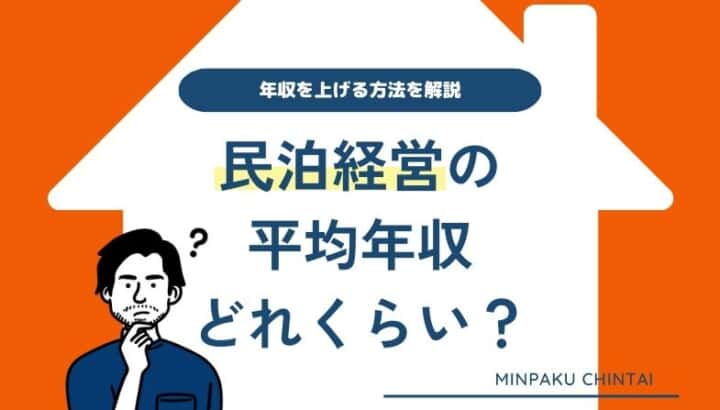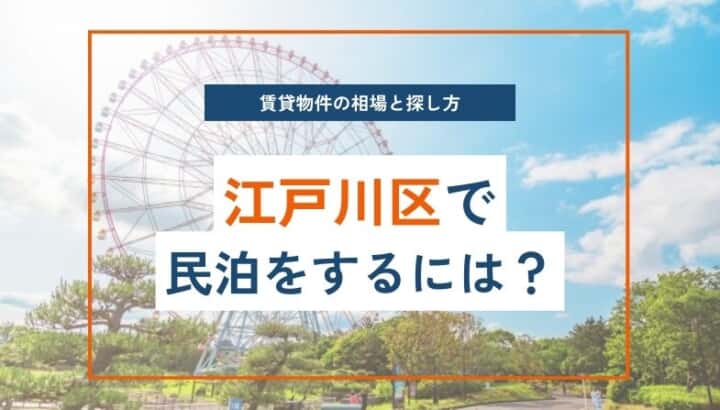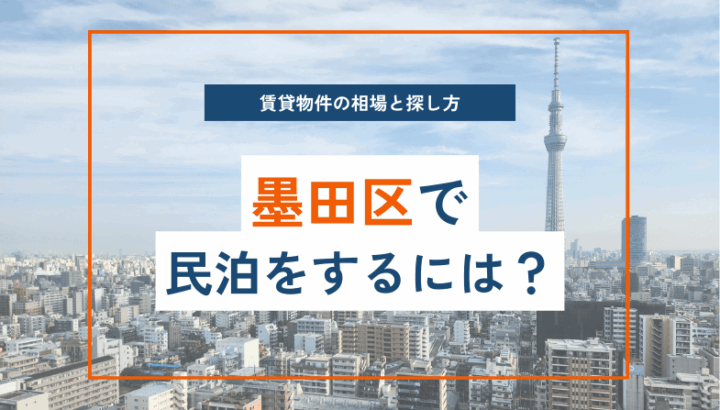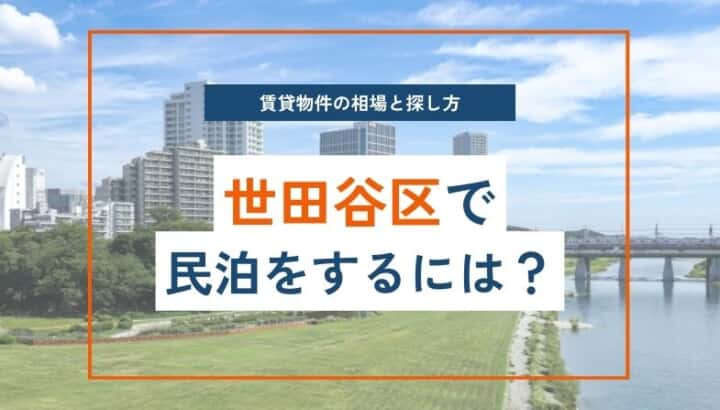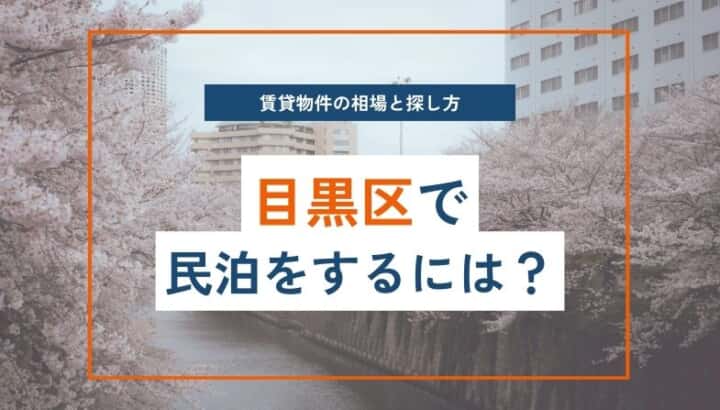旅館業法とはどんな法律?民泊新法との違いや改正内容、許可申請の手順を解説
近年、訪日観光客の増加やライフスタイルの変化に伴い、「民泊」が注目を集めています。しかし、宿泊施設を運営するには法律の理解が不可欠です。特に旅館業法と民泊新法(住宅宿泊事業法)は、それぞれ異なるルールを定めているので、違いが分からず悩んでいる方は多いのではないでしょうか。
本記事では、旅館業法の概要や民泊新法との違い、最新の改正内容について詳しく解説します。興味のある方はぜひご覧ください。
CONTENTS
旅館業法とは

旅館業法とは、日本国内で旅館やホテルといった宿泊施設を営業する際に必要な基準を定めた法律です。旅館業を営むためには、施設の衛生管理や防火対策、適切なサービス提供などが求められ、自治体から営業許可を取得する必要があります。
この法律の目的は、宿泊者の安全と快適な滞在を確保し、公衆衛生の向上を図ることにあります。旅館業法は、宿泊施設の種類を「ホテル営業」「旅館営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」の四つに分類し、それぞれの形態に応じた要件を規定しています。
特にホテルや旅館においては、一定以上の客室数や設備基準が設けられており、厳格な審査を通過しなければ営業できません。
旅館業法と民泊新法の違い

旅館業法と民泊新法(住宅宿泊事業法)は、宿泊施設の営業形態に応じた規制を設けるための法律ですが、それぞれの目的や要件には大きな違いがあります。
旅館業法は、主に旅館やホテルといった事業者が運営する宿泊施設を対象としており、設備や衛生管理の基準が厳しく設定されています。一方、民泊新法は一般の住宅を活用して短期的な宿泊サービスを提供するケースを想定しており、旅館業法よりも規制が緩和されています。
民泊新法では年間180日までの営業が認められ、自治体への届出を行うことで運営が可能になります。しかし、地域ごとに条例によって営業制限が設けられることもあり、すべてのエリアで自由に運営できるわけではありません。
改正された旅館業法の要点・ポイント

ここからは、改正された旅館業法の要点・ポイントについて紹介します。
迷惑客に対する対応
旅館業法の改正により、宿泊施設の運営者が迷惑行為を繰り返す客に対して適切な対応を取ることができるようになりました。これまで、旅館業法では「正当な理由がない限り宿泊を拒んではならない」とされており、実際には迷惑客の宿泊を拒否することが難しい状況がありました。
しかし、今回の改正では宿泊者が他の宿泊者や施設スタッフに迷惑をかけたりする場合、宿泊を拒否できる明確な基準が設けられました。
感染症の防止対策
旅館業法の改正では、宿泊施設の運営者は宿泊者に対して、必要に応じた感染症防止の協力を求めることができるようになりました。
これは2020年の新型コロナウイルスの流行を考慮したもので、宿泊施設においての感染拡大を防止する目的が含まれています。
宿泊者は正当な理由がない限り、運営者の協力の応じなければいけません。
旅館業の種類

ここからは、旅館業の種類について紹介します。
旅館営業
旅館営業とは、日本の伝統的な宿泊施設である旅館を対象とした営業形態です。旅館は畳敷きの客室や和風の建築様式、温泉や大浴場といった施設を備えていることが特徴であり、宿泊者に対して和の文化を体験できる空間を提供します。
ホテル営業
ホテル営業は、主に洋風の建築様式を持つ宿泊施設で行われる営業形態であり、都市部を中心に広く展開されています。ホテルの特徴は、個室ごとにベッドが備えられ、バスルームやトイレが完備されていることが一般的である点です。
また、フロントサービスやルームサービス、レストランなど、多様な施設やサービスが提供されることが多く、宿泊者のニーズに応じた快適な滞在環境が整えられています。
簡易宿所営業
簡易宿所営業は、比較的規模が小さく、簡易な設備を備えた宿泊施設を対象とする営業形態です。一般的に、ゲストハウスやカプセルホテル、ホステルなどがこのカテゴリーに該当し、低価格で宿泊できることが特徴です。
簡易宿所営業の施設は、相部屋形式のドミトリータイプや共同の浴室・トイレを備えていることが多く、バックパッカーや若年層の旅行者、長期滞在者に人気があります。
下宿営業
下宿営業は、長期間にわたって同じ宿泊者に住居を提供する営業形態であり、一般的には学生や単身赴任者、長期滞在者を対象としています。
通常のホテルや旅館とは異なり、下宿では食事の提供が行われることが特徴で、宿泊者は一定の契約期間のもとで生活を送ることができます。旅館業法においては、宿泊日数の制限がなく、継続的な居住が可能な形態として認められています。
旅館業法の主な違反行為と罰則

ここからは、旅館業法の主な違反行為と罰則について紹介します。
無許可営業
都道府県知事は、旅館業が営まれている施設において次条第三項の規定による命令をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該旅館業を営む者(営業者を除く。)その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、旅館業の施設に立ち入り、その構造設備若しくはこれに関する書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
出典:旅館業法
旅館業を営むためには、旅館業法に基づき、都道府県知事の許可を受けることが義務付けられています。
しかし、許可を得ずに違法に宿泊施設を運営するケースが後を絶ちません。無許可営業は旅館業法の中でも特に重大な違反行為とされており、これが発覚した場合には、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。旅館業の許可を受けて営業している場合でも、法律で定められた義務を遵守しないと違反行為となります。
営業中の義務違反
営業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
一 宿泊しようとする者が特定感染症の患者等であるとき。
二 宿泊しようとする者が賭博その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき。
三 宿泊しようとする者が、営業者に対し、その実施に伴う負担が過重であつて他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として厚生労働省令で定めるものを繰り返したとき。
出典:旅館業法
上記に違反した場合は、50万円以下の罰金が課せられます。
都道府県知事に対する命令違反
都道府県知事は、旅館業の施設の構造設備が第三条第二項の政令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該営業者に対し、相当の期間を定めて、当該施設の構造設備をその基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
出典:旅館業法
旅館業を営む事業者は、都道府県知事の指導や命令に従う義務があります。これは、旅館業法が公衆衛生や宿泊者の安全確保を目的としているため、行政機関の監督下で適正な運営を行う必要があるためです。
命令違反があった場合、事業者には6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることがあります。
虚偽報告や検査妨害
旅館業法では、監督機関による定期的な検査や調査が行われることが規定されており、事業者はこれに協力する義務があります。
しかし、虚偽の報告を行ったり検査を妨害したりすると、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
旅館業の許可申請の手順

ここからは、旅館業の許可申請の手順について紹介します。
事前相談を行う
旅館業の許可申請を行う前に、保健所へ事前相談を行いましょう。保健所に相談することで宿泊施設を運営するための要件や必要な書類、具体的な手続き方法を教えてくれます。
すでに宿泊施設を運営したことのある人であれば、申請をスムーズに進められますが、ゼロから始める人は事前相談しておくことをおすすめします。
申請書類の準備する
旅館業の許可申請を得るには、以下のような書類が必要です。
・許可申請書
・建物配置図
・電気設備図
・換気設備図
・給排水設備図
・周辺地図
・各階平面図
・定款や登記事項証明書(法人のみ)
・施設の構造設備概要図面
・客室の内訳
・消防法令適合通知書
・検査済証の写し
申請書類はかなり多いので、旅館業を運営することを決めた段階で各種書類を集めておきましょう。
旅館業許可申請を行う
書類の準備が整ったら旅館業許可申請を行います。申請先は、施設の所在地を管轄する保健所や自治体の担当部署となります。
必要書類が欠けていると申請許可が下りないので、事前に書類が不足していないか確認しておくと良いでしょう。
保健所の立入検査
旅館業の許可を取得するためには、保健所による立入検査を受ける必要があります。この検査では、施設が法的要件を満たしているかを確認するため、客室や浴室、共用スペースなどの状況が細かくチェックされます。
立入検査の結果、問題がなければ許可が下りることになりますが、不備が見つかった場合は改善後に再検査が行われることになります。そのため、事前にしっかりと施設の準備を整え、検査に備えることが重要です。
営業許可書の交付
保健所の立入検査に合格すると、最終的に営業許可書が交付されます。営業許可書は、施設が法的に適正な基準を満たしていることを証明するものであり、これを取得した後に正式に営業を開始することができます。
許可書が交付されたら、宿泊者が見やすい場所に掲示することが義務付けられているので、忘れずに掲示しておきましょう。
旅館業法を守って適切に運営しよう
宿泊施設を営業するためには、旅館業法の許可申請を行う必要があります。
旅館業法に違反行為した場合は罰則があるので、申請許可が下りても法律を守って適切に宿泊施設を運営しましょう。
ただ、旅館業法の規則はやや細かいため、運営前には規則に目を通しておくことをおすすめします。